押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです



釜石駅駅前広場に建つ大島高任像でございます。日本初の商用高炉、西洋式高炉を釜石に建造した人で、日本近代製鉄の父と呼ばれている方なのだそうですよ、そこの奥さん(←どこの奥さんだって聞いてるのにw)。
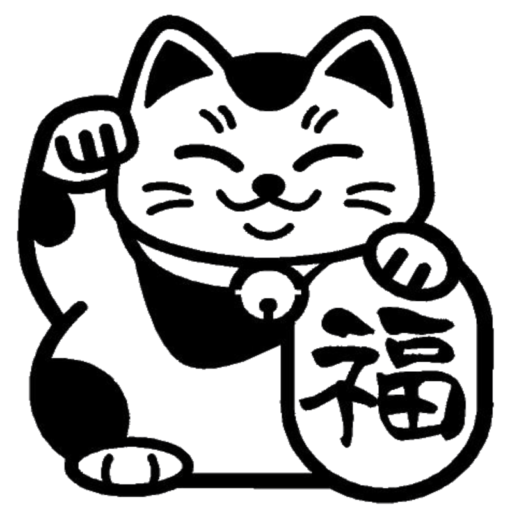 DoraNeko
DoraNeko釜石駅



釜石駅駅前広場に建つ大島高任像でございます。日本初の商用高炉、西洋式高炉を釜石に建造した人で、日本近代製鉄の父と呼ばれている方なのだそうですよ、そこの奥さん(←どこの奥さんだって聞いてるのにw)。
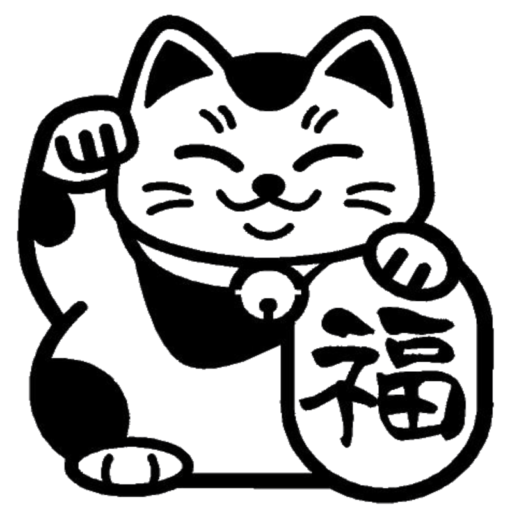 DoraNeko
DoraNeko釜石駅
WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
お気軽にコメントをお寄せください
コメント一覧 (1件)
Wikipediaから引用
大島 高任(おおしま たかとう、文政9年5月11日(1826年6月16日) – 明治34年(1901年)3月29日)は、明治時代の鉱山学者。父・大島周意は藩医として盛岡藩に勤めた。文政9年5月11日(1826年6月16日)、盛岡仁王小路にて盛岡藩侍医・大島周意の長男として生まれる。天保13年(1842年)17歳で留学、江戸で蘭方医の箕作阮甫や坪井信道に師事し、長崎では採鉱術を学ぶ。嘉永6年(1853年)、水戸藩主の徳川斉昭から招かれて那珂湊反射炉を建造。大砲の鋳造に成功するが、原材料が砂鉄の為にその性能は高くはなかった。西洋と並ぶ高品質な鉄を造るべく、良質の鉄鉱石が産出する大橋(釜石)の地にU・ヒュゲーニン著の「ロイク王立鉄製大砲鋳造所における鋳造法」を参考として西洋式高炉を建造、安政4年12月1日(新暦1858年1月15日)に鉄鉱石製錬による本格的連続出銑に成功する。これは商用高炉としては日本初であり(なお、日本において高炉による初出銑は鹿児島の集成館高炉によるもので、安政元年(1854年)のことである)、大島は後の明治政府においても技術者として高く評価され、鉱業界の第一人者として活躍したことから日本近代製鉄の父と呼ばれている。