押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです



塩山駅南口、塩山駅前観光案内所付近で見掛けた旧塩山市のマンホール蓋でございます。大菩薩峠が描かれておりますな。
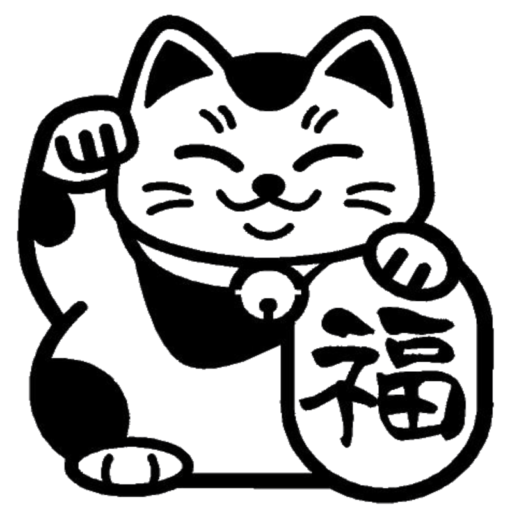 DoraNeko
DoraNeko塩山駅



塩山駅南口、塩山駅前観光案内所付近で見掛けた旧塩山市のマンホール蓋でございます。大菩薩峠が描かれておりますな。
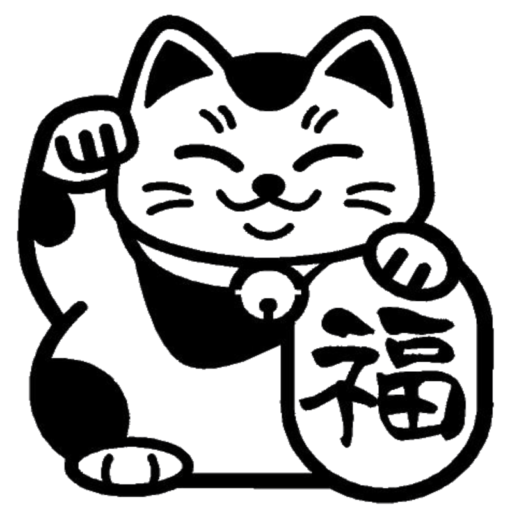 DoraNeko
DoraNeko塩山駅
WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
お気軽にコメントをお寄せください
コメント一覧 (1件)
Wikipediaから引用
大菩薩峠(だいぼさつとうげ)は、山梨県甲州市塩山上萩原と北都留郡小菅村鞍部の境にある峠。標高1,897 m。大菩薩嶺(標高2,057m)の南方約2kmに位置する尾根の鞍部である。国中方面からは、萩原越や大菩薩越、青梅通とも称された。『甲斐国志』によれば「大菩薩」の由来は複数あり、源義光(新羅三郎)が峠越えの際に八幡大菩薩に祈念したとする説、あるいは上萩原の神部神社に由来するとする説が紹介されている。そのほかにも、位の高い僧が峠に菩薩像を埋めて、水が湧き出て峠の西と東に清流となって流れ落ちるように祈願したところ、その水は東に多摩川、西に笛吹川をつくったといわれる伝説があるほか、かつての峠に妙見大菩薩(みょうけんだいぼさつ)が祀られていたともいわれている。1913年(大正2年)から1944年(昭和19年)の32年にわたって『都新聞』に連載された、中里介山の未完の大河小説『大菩薩峠』で広く知名度があり、大菩薩峠から流れ出す多摩川流域の自然や、そこを往来した人々に触れたことで介山の人格や思想形成に大きく影響したともいわれている。1954年(昭和29年)には記念碑が立てられ、介山祭も開かれている。紅葉の名所で、毎年、10月の中旬から下旬にかけて見頃となる。