押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです



紀州街道沿いにある史跡の郷学所跡でございます。堺における郷学所は江戸時代から明治初期にかけて開設された、庶民を対象にした教育機関でございますね。つまりは小学校の前身でございますね。
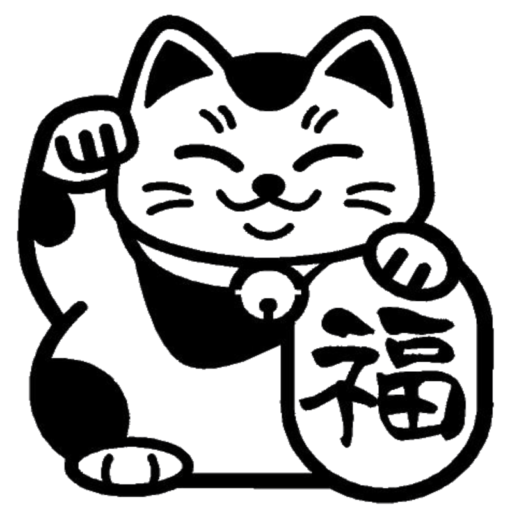 DoraNeko
DoraNeko郷学所跡



紀州街道沿いにある史跡の郷学所跡でございます。堺における郷学所は江戸時代から明治初期にかけて開設された、庶民を対象にした教育機関でございますね。つまりは小学校の前身でございますね。
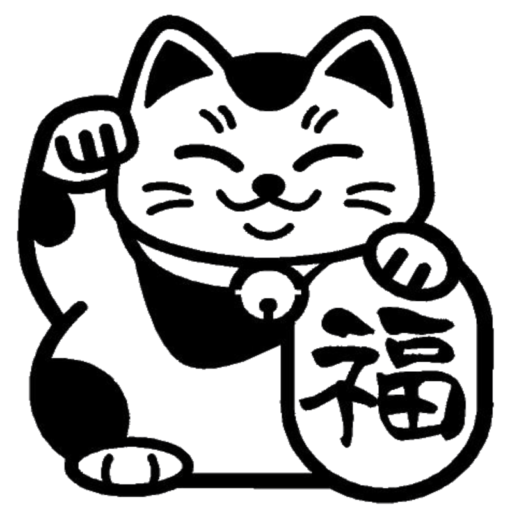 DoraNeko
DoraNeko郷学所跡
WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
お気軽にコメントをお寄せください
コメント一覧 (1件)